PROJECT TALK
徳島県 新町川河口に
橋上部工を架設せよ
慢性的な渋滞に悩まされていた徳島中心部からの道路交通網。
その渋滞緩和を目指し、新町川河口の河川上に新たに橋を架け、
津田ICと徳島東ICをつなげるプロジェクトが立ち上がりました。
架設するのは、実に橋長500m、支間長250mという、国内最大級の鋼3径間連続綱床版箱桁橋。
類を見ない規模となる橋梁工事の架設を担った深田サルベージ建設。
重責ミッションへの挑戦を、主要メンバーたちが振り返ります。
PROJECT MEMBERS

-
大阪支社 四国営業所 所長中野 祐三 2000年入社
- 現場監督として、JVとの折衝・調整、工程管理、詳細計画の方針決定を担当。

-
西日本支社 工事課大和田 洋一 2006年入社
- 主に台船艤装作業のとりまとめと、架設現場の計画検討・現場管理などを担当。

-
大阪支社 四国営業所原 佑太 2016年入社
- 主に海上起重機船の現場係留設備関連の業務と、架設現場の片づけを担当。
若手中心で臨む国内最大級の橋梁工事。

まずこの工事の概要を当社視点でざっくり説明すると、元請けである「川田・横河・MMB特定建設工事共同企業体(以降:JV)」から発注を受けた当社が、JVの各工場で製作された4つの橋梁ブロックを、起重機船を用いて吊り上げて台船に搭載し、徳島港内の準備地まで海上輸送した後、再び起重機船を用いて吊り上げ、港内移動して架設するというもの。

工事自体は2020年でしたが、受注に向けた活動はもっと前から進めていましたね。

当社の関わりとしては、工事の基本計画を検討していたコンサルタント会社に、工事の懸念事項や工事費算出といった側面で情報提供するところから。それが2017年。実は当初より、異なる工法を提案していた他社と競合していて、どちらの工法が採用されるかわからない状態だったので、JVが工事を正式受注したあたりから、JVへの営業活動を強化していった。

具体的には、当社のどのような点をアピールしたんですか?


要は総合力と言っていいかな。第一に今回の工事では、長崎、香川、大阪の堺など、異なる場所から橋梁ブロックを浜出しする必要があったのだけれど、それぞれの海域の特性を熟知している技術メンバーがいること。第二に、そういった強みを生かして事前に精度の高いシミュレーションを行うことによって、工事リスクを低減できること。第三に、工期が秋の台風シーズンであるため、柔軟なスケジュール対応が求められたが、当社は各種船舶を潤沢に保有しており、対象期間中、優先的にそれらを使用できる体制を組めること。

なるほど。それらが総合的に評価されたと…。

そう。そして2019年に当社の受注がほぼ内定した。

それから、四国営業所内に当プロジェクトの工事事務所が開設され、大和田さんや私も関わり始めて、細かい工法や作業手順の検討、事務手続きなどを進めていきました。

プロジェクトに呼ばれてまず驚いたのは、今回の実務メンバーのほとんどが20代中盤から40代以下という比較的若いメンバーだったことです。

確かに、この規模の工事経験がないメンバーが多かった。会社として、そろそろ次世代に経験させて技術を継承していかないといけないタイミングだったので、若手中心の布陣で臨むことになった。それにしては、国内最大級規模の工事ということで、ハードルは高かったかもしれない。ただその分、やりがいは申し分なかったし、みんなの成長につながったんじゃないかな。
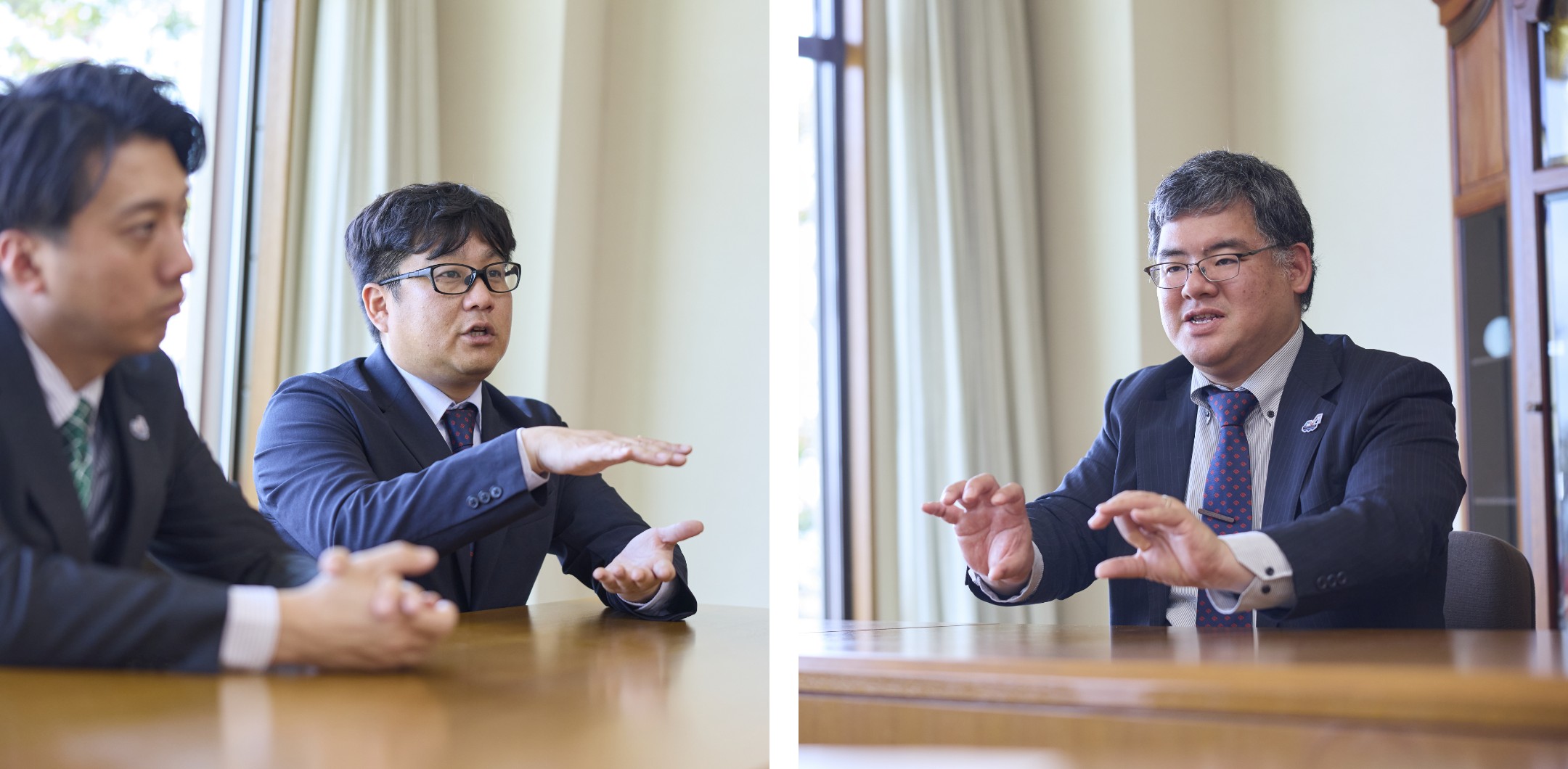

急きょ条件変更となった、係留現場環境。

やりがいや成長はその通りだと思います。たとえば私は主に、現場における起重機船の係留設備を担当したのですが、それまでこれだけの規模の工事に携わったことがなかったので、あまりの作業量の多さに、初めは何から手をつければよいのかわかりませんでした。

今回は特に、通常の工事では当社が担当しないところまで手がける必要があったということも大きかったのでは?

はい。これまで私が担当してきた工事では、たとえば起重機船の係留時に必要になる養生材などは、お客様側で設置していただいていたのですが、今回はそれも含めた一式発注ということで、当社側で設計や設置をする必要がありました。そのほか、係留のために陸上に設置する、アンカー代わりのウエイトについても当社側で設置を担当しました。

JVとしては、工期も短いなかで、すべて深田に任せたほうが確実で効率が良いという判断があったと思う。

どのような設置方法が良いのかという検討も、とにかく初めてで判断がつかないので、中野さんをはじめ周囲の皆さんからいろいろとアドバイスをもらいながら進めていきました。


もう一つ、大きな課題となったイレギュラー事項としては、現場環境の条件変更というのがあったね。

桟橋ですね…。架設工事の前工程として、橋梁ブロックを架設するための下部工(橋脚)の設置があるわけですが、それには陸上からアクセスするための桟橋が必要で、当初計画では、当社が橋梁ブロックを架設する時点で、桟橋はすべて撤去されているはずでした。ところが、前工程のスケジュールがどんどん後ろに倒れてきて…。

それでも橋梁の開通日はすでに決まっていて、架設の工期はずらすことができない…。

そうなんです。本来であれば開放された海上に係留するはずだったので、それを前提に計画を立てていたのですが、桟橋が残置された状態という条件変更により、あらためて計画を組み立てていくことになりました。

そこでは、ベテランの大先輩から係留アイデアを最初に出してもらったけれど、それが大きかった。経験の浅い自分たちだけでは、この条件変更にうまく対応できなかったと思う。

おっしゃる通りです。今回、若手に任せてはもらったものの、要所要所で上の皆さんからサポートしていただいたのが、本当に勉強になりましたし、経験に裏打ちされた深田サルベージ建設の技術力をあらためて実感する良い機会でもありました。

3463tを支える、かつてない台船艤装。

私は主に、橋梁ブロックを海上輸送するために用いる台船艤装に関するとりまとめを担当していましたが、これが当社でもかつてないほど大がかりな艤装とあって、かなり苦労しました。

ブロック4つのうち3つが大ブロックで、長さは160m、幅は28m、高さは7mに及び、重さは3000tをゆうに超える。これを運ぶとなると、一筋縄ではいかない。

はい。台船というのは、資機材・部材などを乗せるための広大な平べったい甲板を持つ船ですが、この甲板に橋梁ブロックを直接置くわけにはいかないので、配置用の脚をいくつか設置する艤装が必要でした。ところが、その脚が尋常ではない大きさだった。

いちばん大きなブロックが3463tだからね。

それだけの重量のものを支えるのに必要な脚の大きさと強度を本社所属の技術本部に計算してもらったりと、本当に未経験の領域でした。しかも、ブロックは160mを超える長さなので、台船からはみ出すかたちで搭載することになります。


当然、海上はいつも凪だとは限らない。

そうなんです。船が揺れて、はみ出したブロックの先端部分が海に浸かることがないよう、脚には高さも必要になってくる。結果、これまで目にしたことのない4段重ねの脚を艤装することになりました。

艤装地でも頭を悩ませていましたね。

そう。台船自体がかなり大型で、艤装工期も数週間に及ぶ。それだけの間、この大型船を係留し続けることのできる岸壁を確保する必要があり、場所の選定から予約、周辺への周知などに奔走しました。

しっかり準備をした甲斐あって、艤装作業自体は大きな問題もなく進めることができたのでは?

周囲のサポートのおかげです。不安な点が出てきたら、すぐにその分野に詳しい人に確認をとるようにしていました。また、作業員の皆さんとも常にコミュニケーションをとりながら、先を見据えた手配をし、施工に滞りがないように努めていました。

深田にしかできない「大サーカス」。

それぞれ担当業務においてヤマ場というものがあるけれど、自分としては今回、現場での架設よりも、多度津での浜出しがヤマ場だったと感じている。

あれは確かに大変な現場でしたね…。

橋梁ブロックはJVの各工場で製造されているので、起重機船と台船がそこまで行って、浜出しをしないといけない。多度津の場合は、浜出しの現場へ行く航路の途中に海上電線が張ってあり、起重機船のクレーンを目いっぱい倒さなければ、電線の下を通過できない。さらに、現場海域も浅いため、起重機船の動きに制限がある。

それも、満潮時でもなく干潮時でもなく、中間潮位の1日の間で限られた時間帯という条件付き。かつ、運航している小型フェリーの航行がない時間帯で、という新たな制約もありました。

そう。だから浜出し作業も時間との闘いで、もし作業に手間取って出発が遅れると、潮位が上がって帰路で電線下を通過できなくなる。潮位が下がると起重機船が動けなくなる。加えて、浜出し現場がまた狭かった。こればかり言っているが、本当に当社で経験したことのないほどの、狭く入り組んだ現場。そして水深も浅いので自由がきかない。

社内のこれまでの工事実績で得た知見では、もはや方法が見つからないというところから検討がスタートしましたね。


通常の方法ではどう考えても無理。だから、これまでやったことのないアイデアを考えるしかなかった。現場の地図とにらめっこをしながら、起重機船と台船、そして橋梁ブロックの動きを、難解なパズルを解くように何度もシミュレーションして、「もうこれしかない」という方法を組み立てた。

「これができたらサーカスだ」と言われましたね(笑)。

自分でもそう思った。でもやるしかない。

当日の現場では、中野さんが総指揮の役割を担って。

深田サルベージ建設の作業員だけで約50人。さらに、JVの工場側にもサポートしてもらう必要があり、そちらも約50人。総勢100人くらいでチャレンジする、練習なしのぶっつけ本番の大サーカスという感じだった。呼吸が合わなければ事故にもつながりかねない。動くものの場所とタイミングをシビアに見計らいながら、指示を出していった。

160mの橋梁ブロックを動かすサーカスですからね。見ていてドキドキしました。

こっちはそれ以上にドキドキしていたかも。でも、あの場にいた全員が気持ちを一つにしたおかげで、無事にプラン通りにやり切ることができた。プレッシャーもあったので、できたときはほっとした。「やればできるもんだな」と深田の実力が上がったような手ごたえも感じたし、JVの担当者さまから「これはもう深田さんにしかできないね」と言われたときには、達成感で胸がいっぱいになった。

それぞれの成長、それぞれのやりがい。

その後、現場での架設自体は、天候にも恵まれて、多少のイレギュラー要素はあったものの、おおむね順調に進んだ印象ですね。

そうだね。当社にとっても未経験の規模の工事なので、あらゆる状況を想定して細かくシミュレーションし、とにかくみんなで意見を出し合いながら周到に準備をしたのがよかったのだと思う。

現場の作業員メンバーとの意思疎通も非常にうまくいったと感じています。

そこは私も強く意識し、心を砕いていました。安全衛生面も含めて、作業の細部について作業員とマメに打ち合わせをすることで、現場で状況が変わっても柔軟に対応できるように努めました。

お互いの連携については、全員が意識していたんだろうね。工事の当日には、メンバー全員が「何をすればいいのか」という共通認識をしっかり持つことができていたので、迷いがなかった。全員が自分の職責をまっとうしたからこその工事完遂だったと思う。

準備期間の打ち合わせの日々がなつかしいですね。


夕方から毎日進捗確認をして。難しい課題ばかりでしたが、意外とみんな明るくて、前向きに意見交換していました。

プロジェクト事務所を解散するときは、少し寂しい気持ちだったな。

私も、毎日が充実していただけに寂しく感じました。このプロジェクトの担当になったとき、最初は自分の未熟さを痛感して落胆した時期もありましたが、周囲の人に助けてもらいながら精一杯取り組んで、これだけ大きな橋梁架設に携わることができました。架設当日、一般の方々が数多く工事の見学に来られているのを目にして、「こんなにも注目されていたんだ!」とこれまでの自身の作業を誇らしく思いました。

国内最大級ということもあるけれど、やはりそれだけ社会的な影響力の大きな橋梁であり、地域の人々の期待が大きかったんじゃないかな。渋滞の緩和に貢献できたのなら、とてもうれしく思うし、やりがいも感じています。あとは、力を合わせることの大切さもあらためて実感しました。深田サルベージ建設きっての一大プロジェクトでしたが、みんなで役割分担をして協力し合い、計画が力強く前へ進んでいく様子は、当社を誇らしく感じるほどでした。みんなでやればなんとかなる!と。

それぞれが自分なりのやりがいを感じることができたプロジェクトだったと思う。私自身は、自分がこれまで経験してきたことを出し切り、下の世代に伝承することを一番に考えていた。机上だけでは決して生まれない発想を大切にし、一人ひとりが自主的にアイデアを出し合えるようになればいいと考えていた。それは、ある程度達成できたように思う。私自身はもちろんメンバー全員、今回のプロジェクトで得られたものを、また次の現場で生かしていきたいね。

規模は少し小さくなるものの、すでに次の橋梁架設プロジェクトが進行中ですので、さっそく生かしたいと思います。

私も、チャンスがあればまたぜひ橋梁架設工事に携わることができるよう、積極的にチャレンジしていきます。

心強い限りだ。引き続き、深田だからこそできる仕事をみんなでかたちにしていこう!
